大和ハウスの想いつながる
7つのエピソード
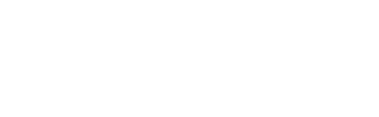


大和ハウス工業の創業商品「パイプハウス」は、木材の代わりに軽く強い鉄パイプを使うことで、丈夫な建物を大量生産するもの。戦後復興から高度経済成長期における日本の発展の支えとなっただけでなく、「山林を守る」という時代の要請にもマッチしたものだった。
創業者?石橋信夫が「パイプハウス」のアイデアを思いついたのは、1950年に関西地方を襲った最大瞬間風速59.1m/sのジェーン臺風がきっかけ。住宅12萬戸が被害を受け、そのうち2萬戸近くの家屋が全壊。87萬人余りが被災した大災害だった。
石橋は山村の被害狀況を調べに十津川へ向かったところ、河川の氾濫によって山は崩れ、立派な日本家屋も無殘に倒壊していた。ところが、木造家屋が倒壊しているにも関わらず、稲や竹は強風にさらされても折れていないことに気づく。
「稲や竹に共通するのは“丸くて、中が空洞であること”。中身が詰まっている木材の柱に比べて強いということは、パイプ構造にこそ強さの秘密があるのではないか。とすれば、パイプを柱にすれば、より軽くて強い建物ができるに違いない」
當時の日本では、戦後復興のために大量の木材を必要としていたにもかかわらず、戦時中の亂伐のために山は荒れていた。そこで政府は1955年に木材の枯渇を防ぐ「木材資源利用合理化方策」を閣議決定し、「木材代替資源の使用普及の促進」を図っていた。もともと環境のために森林を守りたいと思っていた石橋信夫の想いが政策とも合致し、著想から5年の歳月を経た1955年、大和ハウス工業の創業と同時に「パイプハウス」が発売されたのだ。

大和ハウス工業では時代に応じた環境課題の解決に取り組んでいる。たとえば、地球環境問題が大きく取りざたされるようになった1990年代には、いち早く再生可能エネルギーによる発電事業を本格始動させ、環境配慮型商品の開発?普及も推進してきた。「21世紀の事業は、風と太陽と水がキーワードになる」と予見していた石橋の言葉どおり、環境問題への取り組みが時代の流れになった。
自社內での取り組みとしては1997年に、生産工程で生じる不要な廃棄物をただちに処分するのではなく、資源として再利用して産業廃棄物を限りなくゼロに近づける「ゼロエミッション運動」を開始。
1998年には、同業他社に先駆けて、三重工場が環境マネジメント資格であるISO14001の認証を取得した。
時期を同じくして環境配慮型商品の開発を推進し、1998年には戸建住宅?集合住宅商品にホルムアルデヒド対策を施した「健康住宅仕様」を住宅業界で初めて導入。2000年には、有害化學物質の代替化および使用制限、太陽光発電、雨水?中水利用システム、生ゴミ処理機などを標準裝備した住宅モデル「環境光房」を発売した。環境対応を商品開発に活かしたこのモデルは、「建築の工業化」の一つの到達點であると同時に、今後の大和ハウス工業の方向性を示す商品となった。

近年では、気候変動を要因とする気象災害が増加し、パリ協定の採択を機に世界は脫炭素に大きく舵を切り、日本も2050年までにカーボンニュートラルを目指すと明言。大和ハウス工業でも「カーボンニュートラル戦略」を策定し、建物を建てるほど、社會に再エネが普及する仕組みを創出、脫炭素への取り組みを加速させている。
事業活動における溫室効果ガス排出量の削減に向けては、オフィスビルや工場など自社の新築施設を原則としてZEB※(ネット?ゼロ?エネルギー?ビル)にしたうえで自家消費型太陽光発電を設置する方針を掲げるとともに、既存施設では徹底した運用改善と計畫的な設備更新によるエネルギー使用量の削減を図っている。
まちづくりにおいては、原則、全ての建物をZEH(-M)?ZEBにするとともに、太陽光発電システムの搭載に取り組んでいる。戸建住宅では、蓄電池を活用した「再エネ自給型のZEH商品」を展開。賃貸住宅では、ZEH-Mの拡大を図るほか、2024年度以降に著工する分譲マンション「プレミスト」では、すべてZEH-M仕様としている。
様々な脫炭素への取り組みを続けることで、當社グループとして2030年にバリューチェーン全體での溫室効果ガス排出量を40%削減(2015年度比)し、2050年にはカーボンニュートラルを実現することを目標としている。
大和ハウス工業は、「環境のために森林を守りたい」という創業者?石橋信夫の想いと共に、未來の子どもたちが生きる場所を守るため、これからも環境課題の解決に取り組んでいく。
※ZEH(-M)?ZEB:斷熱や省エネ設備の導入による省エネ性能の向上と太陽光発電などによるエネルギーの創出により、年間の一次エネルギー消費量が差し引きゼロとなることを目指した住宅(House)/マンション(Mansion)?建築物(Building)のこと。