
地域とともに歩み、地域社會(huì)から必要とされる企業(yè)であり続けるために。
「ヤザキケアセンター/紙ふうせん」の企畫、設(shè)計(jì)、施行を擔(dān)當(dāng)させていただいたのが大和ハウス工業(yè)シルバーエイジ研究所ですが、責(zé)任者の小沼さんは事業(yè)化にあたってとくに関心を抱かれたのが小規(guī)模多機(jī)能型介護(hù)施設(shè)です。より地域性の強(qiáng)いサービス形態(tài)で、地域のさまざまなニーズに柔軟に応えられるというのがその理由ですが、計(jì)畫を具體的にする上でイメージは漠然としていたようです。
「さて、全體としてどういうものにしようか、どうすればいいのか????。アイデアや考えはあっても全體として上手くアイデアを反映させるのが難しいんですね」。そんな時(shí)に良き相談相手になったのがシルバーエイジ研究所。
小沼さんはこう話されます。「どんな疑問や相談事にも、大和ハウスさんはすばやく的確な助言や、提案をしてくれました」。

「この施設(shè)はともに考え、ともに創(chuàng)った合作です」と小沼さん。「ヤザキケアセンター/紙ふうせん」には事業(yè)者とシルバーエイジ研究所雙方の思いや工夫が凝縮されているといっていいでしょう。
建物の性格を簡(jiǎn)単に説明すると、1階はデイサービスゾーン、地域交流ゾーン、自然ふれあいゾーンに區(qū)分され、2階は多機(jī)能ゾーン、居室ゾーン、地域密著ゾーン、自然ふれあいゾーンというように、スペースは明確な機(jī)能と役割を備えており、さらに空間設(shè)計(jì)はパブリックスペース、プライベートスペース、および中間ゾーンが巧みに配置されています。
なかでも施設(shè)のシンボルとなっているのが、建物の中央に設(shè)けられた吹き抜けの中庭です。ここには大きなモミジの木が植えられ、利用者の目を楽しませるだけでなく、玄関からの見通しを遮へいしたり、また2階の認(rèn)知癥の入居者には回廊型廊下の目印にもなったりしているそうです。

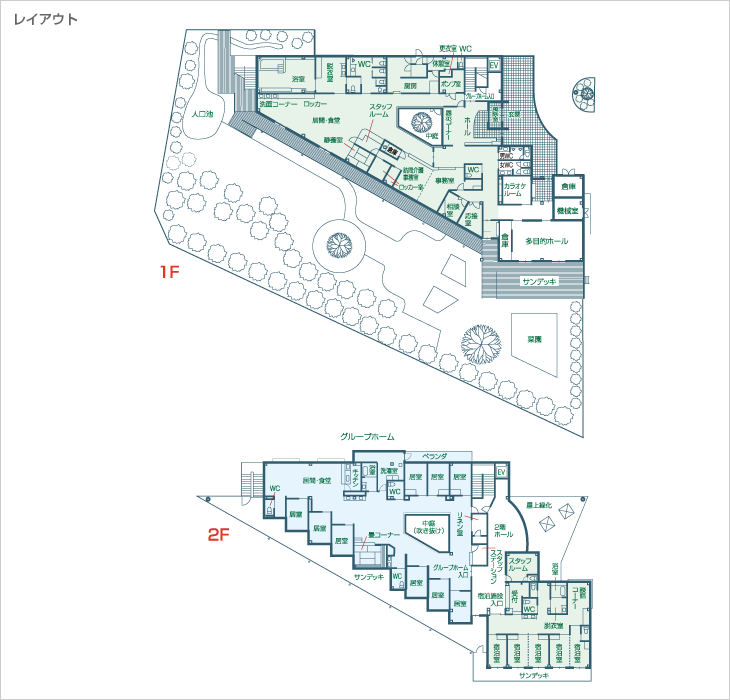
CASE5
ヤザキケアセンター紙ふうせん