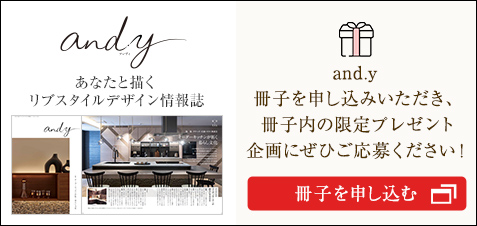子育てにおける、絵本の読み聞かせが果たす役割とは?
読み聞かせの専門(mén)家、絵本作家として活躍中の、
聞かせ屋。けいたろうさんにお話を伺いました。
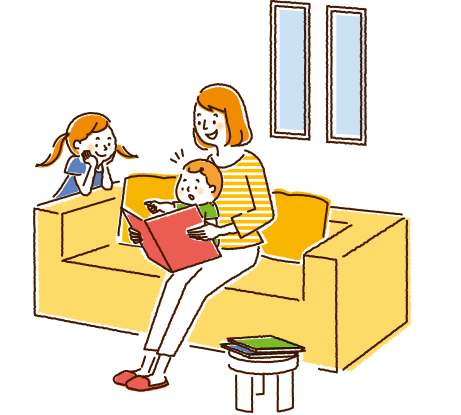
保育の現(xiàn)場(chǎng)で絵本を見(jiàn)ない日はないと言われるほど、子ども達(dá)は絵本が大好きです。絵本の魅力は読み手と聞き手という関係を生み出す點(diǎn)にあります。お父さんやお母さん、保育園?幼稚園の先生が、自分のために聲を響かせお話を読んでくれる。その行為自體が子どもにとっては、とても嬉しいことです。家庭での絵本の時(shí)間は、親子のつながりを育む時(shí)間とも言えるでしょう。共働き世帯の増加など、親子のコミュニケーションが減っている中でも、絵本を通した子どもとの觸れ合いを大切にしてほしいですね。
また、年長(zhǎng)さんや小學(xué)生に成長(zhǎng)した子どもが「絵本を読んでほしい!」と持って來(lái)ることはありませんか。字が読めるようになったばかりだと、文字を読むことに一生懸命で、絵や物語(yǔ)を楽しみきれないのです。読んでもらうことによって、子どもは絵をじっくり見(jiàn)てさまざまな発見(jiàn)をしながら、物語(yǔ)を楽しめます。「自分で読めるでしょう?」と斷らず、読んであげられたら良いですね。
一般的に絵本に初めて觸れるのは、生後6か月からと言われますが、生後3か月でも読み聞かせに反応する赤ちゃんはいます。言葉が分からなくても、楽しい気持ちは赤ちゃんにも屆きます。初めての絵本にお?jiǎng)幛幛胜韦稀?~2歳向けの「赤ちゃん絵本」。一緒に寢転がったり、向かい合ったり、膝の上に座らせたり、いろんな姿勢(shì)で自由に楽しんでみてください。
海外では赤ちゃん絵本は言葉や色、形を教える初等教育の本として扱われることも多いですが、日本の場(chǎng)合は親子の関わりを生み出すものが主流です。指をさしたり、くすぐり合ったり、顔を見(jiàn)合ったりと、スキンシップが生まれる工夫が多くみられます。例えば、『たっちだいすき』※1はハイタッチをしながら楽しめる絵本。『ぶう ぶう ぶう』※2では親子で一緒に「ぶう」と聲を出して読み進(jìn)められます。ば行、ぱ行、ま行など、赤ちゃんが発しやすい両唇音が多用されるのも赤ちゃん絵本の特徴です。赤ちゃん絵本で、親子の楽しいひと時(shí)を過(guò)ごしませんか。
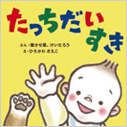 ※1『 たっちだいすき』聞かせ屋。
※1『 たっちだいすき』聞かせ屋。
けいたろう 文、ひろかわ さえこ 絵
(アリス館)
 ※2『 ぶう ぶう ぶう』
※2『 ぶう ぶう ぶう』
おーなり由子 文、はた こうしろう 絵
(講談社)
聞かせ屋。けいたろうさん
子どもから大人まで幅広い世代に絵本の魅力を伝える、聞かせ屋。日本全國(guó)で読み聞かせ、絵本講座、保育者研修會(huì)の講師を擔(dān)當(dāng)。元保育士で絵本作家としても活躍。一児の父。著書(shū)に『どうぶつしんちょうそくてい』(アリス館)、『たっちだいすき』(アリス館)など。
2018年8月現(xiàn)在の情報(bào)となります。
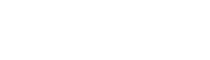

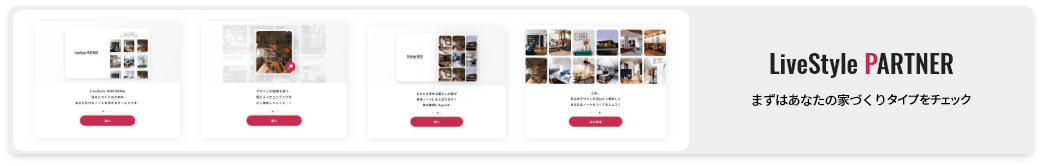


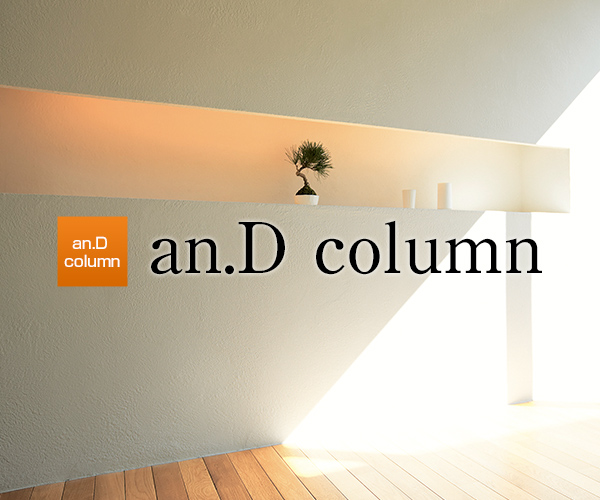
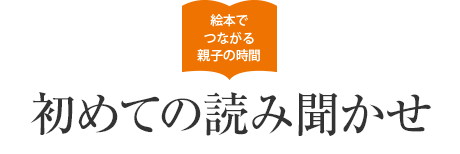


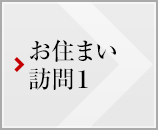
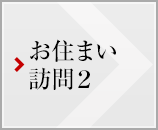
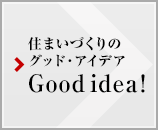


![[あなたと描くリブスタイルデザイン情報(bào)誌 and.y] and.y 冊(cè)子をお申し込みいただき、冊(cè)子內(nèi)の限定プレゼント企畫(huà)にぜひご応募ください!冊(cè)子を申し込む](/tryie/and/common/images/bnr/bnr_pre2.jpg)