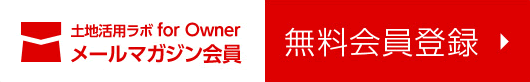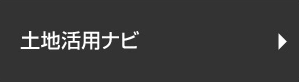コラム No.43
コラム No.43トレンド
新たなまちづくり手法「スマート?プランニング」とは
公開日:2017/11/30
平成29年7月、國土交通省都市局都市計(jì)畫課都市計(jì)畫調(diào)査室は、新しい都市計(jì)畫の手法として、「スマート?プランニング実踐の手引き(案)」とりまとめました。
この內(nèi)容をもとに、都市開発?まちづくりの新たな手法であるスマート?プランニングについて紹介します。
スマート?プランニングとは
スマート?プランニングとは、個人の行動データをもとに、歩行や自転車、車などの回遊行動をシミュレーションすることで、施設(shè)の配置やまちづくりをプランニング(計(jì)畫)する手法のことです。
現(xiàn)在、個人の行動データとして、スマートフォンやGPSロガ-などからのGPSデータ、民間企業(yè)によるスマートフォンアプリ等で取得されるビッグデータやWi-Fiによるログデータ等、さまざまなデータがあります。
そして、このようなきめ細(xì)かい行動データをもとに、交通関連データなどを組み合わせ、現(xiàn)在の人の回遊狀況を把握したうえで、仮の施設(shè)やイベントを設(shè)定し、回遊行動のシミュレーションを行います。そのシミュレーション結(jié)果にもとづいて、計(jì)畫した各施策での回遊行動の変化を評価?検証し、最適な交通システムや施設(shè)、動線づくり、実施すべきイベントなどを計(jì)畫する、これがスマート?プランニングです。
スマート?プランニングが生まれた背景
なぜスマート?プランニングが生まれたのでしょうか。
ひとつには、少子高齢化、人口減少に伴うコンパクトシティ化が望まれるなか、従來よりもさらにきめの細(xì)かい、細(xì)部にわたった計(jì)畫が必要となってきたことがあげられます。自治體の財(cái)源は縮小傾向にありますから、そのためには、実際に駅周辺や人が集まる拠點(diǎn)においてどのような人の回遊が見られるのか、道路空間は効果的に活用されているのか、歩行者や自転車を利用する環(huán)境は適切か、などといった、區(qū)域における詳細(xì)な人の動きを把握する必要があります。
また、今日、スマートフォンのGPSデータや交通系ICカード、ETCカード、Wi-Fiアクセスポイントデータなど、全國のあらゆる場所で、24時(shí)間365日、取得されるビッグデータがあります。
こうしたデータを活用することで、より詳細(xì)な人の動きを収集、分析することが可能になったのです。
従來の計(jì)畫方法との違い
自治體の公民館、図書館等の教育関連施設(shè)や、醫(yī)療福祉施設(shè)等の立地を検討する場合、地図上で人口の分布や密度、交通の利便性などを考慮しながら、地域內(nèi)にある自治體が保有する空き地のなかから立地場所を選定するというのが、従來の一般的な手法でした。
しかし、この方法では、本來どの場所に建てるべきなのかという観點(diǎn)からの計(jì)畫手法として十分ではなく、選定した場所が本當(dāng)に最適地だったのかを検証することは不可能でした。
スマート?プランニングでは、ビッグデータを活用し、個人の行動特性を把握したうえで、施設(shè)配置や道路空間の配分をシミュレーションし、そのときの「歩行の距離?回遊予測」「立ち寄り箇所數(shù)」「滯在時(shí)間の変化」などのデータを見ます。その結(jié)果を受けて、最適な施設(shè)の立地を検討するわけです。
スマート?プランニングを活用することで、これまでの主観的な経験と勘に頼ることなく、データに裏付けられた共通認(rèn)識を持ったうえで、最適な施設(shè)立地を検討することができます。また、計(jì)畫を地域住民に説明、提案する際にも、具體的なデータを示すことができるため、地域住民にとっても分かりやすくなります。
現(xiàn)在、各自治體において、平成26年の都市再生特別措置法の改正により導(dǎo)入された「立地適正化計(jì)畫の策定」が進(jìn)められています。立地適正化計(jì)畫とは、自治體がコンパクトシティ化を推進(jìn)するために、都市誘導(dǎo)區(qū)域や誘導(dǎo)施設(shè)を計(jì)畫することが主な內(nèi)容ですが、その際に、このスマート?プランニングの手法が大いに役立つのではないかと期待されています。
スマート?プランニングの一例
「スマート?プランニング実踐の手引き(案)」では、いくつかの事例が紹介されています。まず、ひとつの事例として、新しいショッピングセンターと古くからある百貨店という、2つの拠點(diǎn)を結(jié)ぶ通りの魅力を高め、回遊性を向上させたいという課題がある場合、下図のように、2つの拠點(diǎn)の中間地點(diǎn)に「仮想のオープンカフェ」を設(shè)置。収集したデータを活用して人の回遊や活用狀況のシミュレーションを行うことで、このような施設(shè)が有効かどうかを確認(rèn)することができるわけです。

また、福祉施設(shè)の最適な配置シミュレーションを行いたい場合、仮に歩いていける距離に設(shè)置し、高齢者がどのように動くことが可能なのかをシミュレーションしてみるといったプランニングが可能になります。

出典:國土交通省「スマート?プランニング実踐の手引き(案)」
ビッグデータの活用に関しては、様々な応用例が次々と考え出されていますが、都市計(jì)畫?まちづくりにおいても、今後、有力な手法となることは間違いないでしょう。