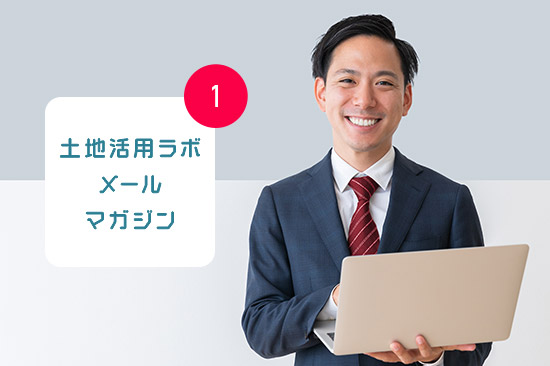コラム No.164
コラム No.164オフィス環境はどう変わっていくのか?オフィス拡張の動きは今後も続くか
公開日:2025/03/31
わが國で新型コロナウイルス感染癥が感染拡大した2020年から5年が経ちました。「5類移行」となった一昨年あたりから出社率は上昇し、オフィス回帰の傾向が強まっています。反面、リモートワークも普及し「5類移行」後も自宅勤務を継続する企業は少なくありません。いわゆるニューノーマル(新常態)時代におけるオフィス環境は今後どう変わっていくのでしょうか。その方向性について考えてみます。
4人中3人以上の出社は26%から63%に上昇
一般社団法人ニューオフィス推進協會が日経ニューオフィス賞への応募企業(160社/2021年から2023年)を対象に実施した「ニューノーマル時代のオフィスづくりに関する調査」(2024年6月公表、以下「報告書」)によると、新型コロナウイルス感染拡大時期(以下コロナ禍)における自粛期間と現在の出社率は正反対の數値を示しています。自粛期間中は76%以上の出社率の會社は26.3%なのに対し、現在は63.8%となっています。言い換えると、コロナ禍では4人中3人以上が出社していた企業が3割を切っていたのに対し、現在その比率は6割強になっており、オフィス回帰が鮮明になっています。
また、オフィス回帰が進むにつれてオフィススペースの拡大を図る企業が増加、160社中94社と6割近い企業でオフィスを拡張しています。拡大?新設されたオフィス空間は、社內の人が自由に集まり、會議や打ち合わせができるオープンミーティングスペースや、自宅勤務者?出張者が自席以外でPC作業や書類のチェックなどができるタッチダウンオフィススペース(一時的に仕事をするためのスペース)など、社內往來がしやすい環境になっているケースが増えています。報告書は、こうした傾向に対して「自席で情報処理を行うデスクワーク中心の働き方から、コミュニケーション主導で作業に応じて場所を選び、ハイブリッドワークの併用も前提とする、適業適所型のワークスタイルへ移行している」と指摘しています。
働き方改革法とコロナ禍がテレワーク後押し?
コロナ禍による「自粛」は、それまでの日常生活を根底から変えました。加えてコロナ禍の前年(2019年)に、いわゆる「働き方改革関連法」が施行されていたことで、テレワークなどの自宅勤務といった新たな働き方への導入機運が一層高まりました。コロナ禍と政府方針が後押ししてニューノーマル(新常態)の取り組みが醸成されたと言えるのではないでしょうか。
報告書によると、働き方改革の支援で企業が重要視しているのは、①社內コミュ―ニケーションの活性化②社內のコラボレーションの推進③自由度の高い柔軟な働き方の拡大―-などです。長期間テレワークを実施したことで社內のコミュニケーションが不足気味になったため、オフィス勤務の復活後には社員に対してコミュニケーション力を上げてほしい、との企業判斷が生まれているのかもしれません。
コロナ緩和後も、テレワークを続ける人は少なくありません。企業は働き方改革の一翼を擔っています。またこれを機にデジタル化を推進しようと考えています。また、ウイルスの強い感染力を経験したことで、人混みや車內でマスクを著用するなど、日常的に感染予防を取る人も従來に比べて増えています。一方、コロナ禍で學生生活を過ごした社員のコミュニケーション不足も指摘されています。その他、ITの活用や健康?公衆衛生の推進など、企業が今後のオフィス環境づくりで留意すべきことは多岐にわたっています。
自宅勤務と出社、メリハリを利かした使い分けが必要
パンデミックを機に自宅でできる業務は在宅でこなし、出社が必要な仕事は會社に出て処理する。メリハリを利かした勤務環境を継続することが今後の企業活動に求められます。また、自宅と勤務先の中間距離にあるサテライトオフィスの整備も進むと予想されています。「都心だけでなく郊外の拠點についても整備が進めば、より柔軟な適業適所型ワークスタイルの拠點として、その役割が増すことになるだろう」と報告書は指摘しています。
テレワークと會社勤務を適切に運営していくためには、企業の屬性に応じた柔軟な対応が欠かせません。労働生産性の観點から業務に応じて使いわけることが肝要ではないでしょうか。こうした二刀流の働き方は「ハイブリッドワーク」と呼ばれていますが、そのためにはネットワークシステムなどのインフラ整備や、自由度の高いオフィスの改修が課題になります。
コロナ禍によって必然的にリモートワークが登場しました。それは働き方改革を推進する原動力にもなりました。いわば強制的ともいえる狀況で大規模に広がったリモートワークです。コロナ禍がなければここまで働き方改革に対する議論や実踐が生じることはなかったかもしれませんが、新たな選択肢が可能となった現在、改めて新たな働き方を模索することで、新しいワークスタイルが生まれてくるのではないでしょうか。