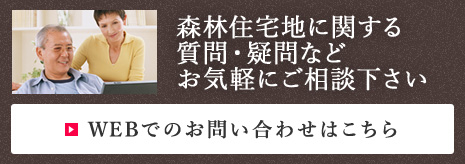國(guó)定公園內(nèi)で過(guò)ごす喜び、自然を贅沢に楽しむ湖畔のリゾート
- 更新日:2010年10月29日
- カテゴリ:自然観察
國(guó)定公園內(nèi)で過(guò)ごす喜び、自然を贅沢に楽しむ湖畔のリゾート
 8月初め、夏のロイヤルシティ蕓北聖湖畔リゾートを訪ねました。夏といっても近くにはブナの原生林やスキー場(chǎng)のある蕓北、日差しは強(qiáng)くても爽やかな風(fēng)が吹いて、気持ち良く散策を楽しむことができました。
8月初め、夏のロイヤルシティ蕓北聖湖畔リゾートを訪ねました。夏といっても近くにはブナの原生林やスキー場(chǎng)のある蕓北、日差しは強(qiáng)くても爽やかな風(fēng)が吹いて、気持ち良く散策を楽しむことができました。まず、現(xiàn)地事務(wù)所を出てB街區(qū)を歩くことにしました。すぐに秋の七草のひとつ、オミナエシをみつけました。近くのノリウツギは、白い裝飾花を數(shù)個(gè)つけているので、まだ開花中のように見えますが、よく見ると花は終わったあと。小さな未熟の実がたくさん円錐狀に固まっています。


■左:オミナエシ(女郎花) オミナエシ科オミナエシ屬
日本全土の山野の草地に生育する多年草。8~10月に黃色い花を枝先に多數(shù)つける。黃色い花を粟(アワ)飯に見立てて「おみなめし」(女郎=昔は白米は男が、女は粟飯を食した)からついたと言う説の他、諸説ある。秋の七草のひとつ。
■右:ノリウツギ(糊空木) ユキノシタ科アジサイ屬
北海道から九州の山地の林縁などに生育する落葉低木~小高木。火山の周辺でも見られるように先駆的にはえる。7~8月、白色の小さな花が円錐狀に咲き、まわりに4弁の花弁をもつ裝飾花をつける。名前は樹皮から和紙を漉くときに使う糊をつくったことからついた。空木は枝が中空なことから。
 花が少ないこの時(shí)期、春から初夏にかけて咲いていた樹々の実が色づきはじめていました。ムシカリは大きな葉の上に赤い実をつけて、少し暗い林の中でもよく目立ちます。ウワミズザクラは白いブラシ狀でおとなしい印象を與える花の時(shí)期と打って変わって、この時(shí)期はちょっとカラフルです。黃色から赤、褐色、黒と変化する段階をひとつの穂で見ることができます。緩やかな坂を上って行くと小さな実をつけた低木が2種類。向き合ってついている葉の間から柄を出し、赤く色づきはじめた実をつけているのはオトコヨウゾメです。実はまだ未熟で平らですが、もう少したつと楕円形の赤い実になります。もうひとつ、上を向いてエンジ色に熟しているのはコバノガマズミです。近い仲間ですが、実のつき方が全く異なります。
花が少ないこの時(shí)期、春から初夏にかけて咲いていた樹々の実が色づきはじめていました。ムシカリは大きな葉の上に赤い実をつけて、少し暗い林の中でもよく目立ちます。ウワミズザクラは白いブラシ狀でおとなしい印象を與える花の時(shí)期と打って変わって、この時(shí)期はちょっとカラフルです。黃色から赤、褐色、黒と変化する段階をひとつの穂で見ることができます。緩やかな坂を上って行くと小さな実をつけた低木が2種類。向き合ってついている葉の間から柄を出し、赤く色づきはじめた実をつけているのはオトコヨウゾメです。実はまだ未熟で平らですが、もう少したつと楕円形の赤い実になります。もうひとつ、上を向いてエンジ色に熟しているのはコバノガマズミです。近い仲間ですが、実のつき方が全く異なります。




■左:ムシカリ(蟲喰、蟲狩)の果実 別名オオカメノキ スイカズラ科ガマズミ屬
北海道から九州の山地に生育する落葉小高木。4~6月、ガクアジサイのような白色の花のかたまりを枝先につける。周囲の裝飾花は5弁。果実は赤色になり熟すと黒色になる。葉は葉脈が目立ち付け根はハート型。葉がよく蟲に食べられるので「蟲食われ」が名前の由來(lái)という説がある。別名は葉の形が亀の甲羅に似ていることからついた。
■左中:ウワミズザクラ(上溝桜)の果実 バラ科サクラ屬
北海道西南から九州の沢沿いなどに生育する落葉高木。4~5月に房狀に白い花を咲かせる。果実は黃色から赤色になり9月頃黒色に熟す。樹皮を傷つけると強(qiáng)い臭気がする。この材の表面に溝を彫り、焼いて亀甲占いに使ったことからついた名。
■右中:オトコヨウゾメ(漢字は不明)の未熟果実 スイカズラ科ガマズミ屬
本州から九州の明るめの林內(nèi)や林縁に生育する日本固有の落葉低木。4~5月、小さな白色の花を枝先に10個(gè)ほどまとめてつける。楕円形の実は數(shù)個(gè)づつまばらに垂れ下がり、9~10月頃赤く熟す。名前の由來(lái)に定説はないが、地方によってはガマズミ類をヨソゾメというところからきている。という説がある。
■右:コバノガマズミ(小葉の萊蒾)の未熟果実 スイカズラ科ガマズミ屬
本州から九州の丘陵地や山地に生育する日本固有の落葉低木。4~5月、白い小さな花を多數(shù)まとまってつける。丸い実は9~11月に赤く熟す。ガマズミに比べ葉が小さく細(xì)長(zhǎng)く、先がとがりぎみ。花の固まり(花序)もガマズミよりひとまわり小さい。
 ゆっくり坂を下っていると林縁の笹の間からはコアジサイが鮮やかな緑色の葉を覗かせています。コアジサイも花は終わり、小さな花のあとが殘っています。裝飾花のない青い花をつけ、花火のようできれいなのですが、なかなか開花時(shí)期にタイミングが合いません。近くのヒヨドリバナでは花の上をハナアブが歩き回っています。公道のすぐ脇にある水路を何かいないかと見ていたところ、ゴソゴソと音がしたので、オーナーさんが庭で何かされているのかと顔を上げると、ニホンアナグマが藪の中から出てきました。こちらには気がついていないようで、公道の側(cè)溝沿いを歩いて行きます。藪の中に逃げ込まれないように少し離れて後を追ってみると、車が通っても全く気にしていない様子。草の間に鼻を突っ込みながら歩き、藪が途切れる手前で藪に入って行きました。夜行性のはずですが、晝間に出て來(lái)ているのにもかかわらずマイペースなので思わず笑ってしまいました。
ゆっくり坂を下っていると林縁の笹の間からはコアジサイが鮮やかな緑色の葉を覗かせています。コアジサイも花は終わり、小さな花のあとが殘っています。裝飾花のない青い花をつけ、花火のようできれいなのですが、なかなか開花時(shí)期にタイミングが合いません。近くのヒヨドリバナでは花の上をハナアブが歩き回っています。公道のすぐ脇にある水路を何かいないかと見ていたところ、ゴソゴソと音がしたので、オーナーさんが庭で何かされているのかと顔を上げると、ニホンアナグマが藪の中から出てきました。こちらには気がついていないようで、公道の側(cè)溝沿いを歩いて行きます。藪の中に逃げ込まれないように少し離れて後を追ってみると、車が通っても全く気にしていない様子。草の間に鼻を突っ込みながら歩き、藪が途切れる手前で藪に入って行きました。夜行性のはずですが、晝間に出て來(lái)ているのにもかかわらずマイペースなので思わず笑ってしまいました。



■左:コアジサイ(小紫陽(yáng)花)の花のあと 別名シバアジサイ ユキノシタ科アジサイ屬
関東地方以西から九州の山野や林縁などに生育する日本固有の落葉低木。5~7月5cmほどの花のかたまりをつける。花はアジサイのような裝飾花(萼片のある花)はなく、ガクアジサイの中央のような小さい花(両性花)の集まり。葉には鋭い切れ込みが入る。紅葉は淡い黃色。名は小さなアジサイから。
■中:ヒヨドリバナ(鵯花) キク科フジバカマ屬
北海道から九州の山地に生育する多年草。草丈1~2cmになる。8~10月、白色から紫色の小さな花をまとめてつける。よく似た花のサワヒヨドリには葉柄がなく、フジバカマは本州の関東以西に生育し、葉は深く3裂する。ヒヨドリの鳴く頃に開花することからついた名。
■右:ニホンアナグマ(日本穴熊) 別名ムジナ 食肉目イタチ科
本州から九州の森林に生息する。夜行性。茶褐色でタヌキに似るが顔が白っぽく、目から顔にかけて黒い模様がある。遠(yuǎn)くて暗かったので、寫りが悪くてスミマセン。
 続いて所々林の間から聖湖を見ながらA街區(qū)のアカマツの多い區(qū)畫へ行ってみました。雑木の多い林とは違い、少し開けた印象を受けます。林床も低木が少なく、マツの落葉の間にノギランやヒカゲノカズラ、イチヤクソウなどがありました。ノギランはちょうど開花中、ヒゲノカズラは胞子嚢を立ち上げていましたが、イチヤクソウは殘念ながら花が終わったあとでした。そろそろ湖畔へ降りようかと戻りかけると、法面の穴の中に大きくて全體的に灰をかぶったようなキノコがありました。あとで調(diào)べてみると、マツと雑木が混在する林に生えるハイカグラテングタケでした。傘が開きかけた物と開ききった物が並び、親子のようで微笑ましかったです。
続いて所々林の間から聖湖を見ながらA街區(qū)のアカマツの多い區(qū)畫へ行ってみました。雑木の多い林とは違い、少し開けた印象を受けます。林床も低木が少なく、マツの落葉の間にノギランやヒカゲノカズラ、イチヤクソウなどがありました。ノギランはちょうど開花中、ヒゲノカズラは胞子嚢を立ち上げていましたが、イチヤクソウは殘念ながら花が終わったあとでした。そろそろ湖畔へ降りようかと戻りかけると、法面の穴の中に大きくて全體的に灰をかぶったようなキノコがありました。あとで調(diào)べてみると、マツと雑木が混在する林に生えるハイカグラテングタケでした。傘が開きかけた物と開ききった物が並び、親子のようで微笑ましかったです。



■左:ノギラン(芒蘭) ユリ科ノギラン屬
北海道から九州の山地の明るい草原などに生育する多年草。6~8月根元に集まった細(xì)長(zhǎng)い葉の中心から花莖を伸ばし、淡黃褐色の小さな花を多數(shù)穂狀につける。花は下から咲き上る。名前にはランとつくがユリの仲間。ノギとはイネ科の植物の花にある針狀の突起で、花の様子が似ていて、葉が一見ランに見えることからついた名。
■中:ヒカゲノカズラ(日陰葛) ヒカゲノカズラ科ヒカゲノカズラ屬
北海道から九州に生育する常緑のシダ植物。針狀の葉をたくさんつけた枝は地を這う。初夏に長(zhǎng)さ3~5cmの胞子嚢穂を直立した枝につける。莖が地上を這うことからカズラ、日陰に多く生育することからヒカゲとついたが、名前に反し日當(dāng)たりの良い所にも多い。
■右:ハイカグラテングタケ(灰神楽天狗茸) テングタケ科テングタケ屬
夏から秋にマツが混ざった雑木林に夏発生する。全體に灰色の粉をかぶったような大きなキノコで、傘は直徑約20cmになる。表面にわたくず狀のイボがあり、開くと少なくなる。柄もやや灰色がかり、柄につく白いツバは薄く落ちやすい。
 聖湖へは事務(wù)所の近くからバークチップが敷かれた遊歩道があります。樹々の間を進(jìn)むと視界が急に開け、きれいな青空を映し込んだ聖湖や周りの山々が見えてきます。近づくと湖面をわたる風(fēng)が気持ちよくて、しばらく景色を見ながら佇んでしまいました。取材中だったことを思い出し、近くを見るとヌマトラノオが白い花をつけて風(fēng)に揺れていました。湖面近くではユウスゲが數(shù)本、長(zhǎng)い莖の先にレモンイエローの花をつけていました。夕方4時(shí)を回っているので、ちょうど咲き始めたところのようです。この花は一日花なので、明日の晝にはしぼんでしまいます。
聖湖へは事務(wù)所の近くからバークチップが敷かれた遊歩道があります。樹々の間を進(jìn)むと視界が急に開け、きれいな青空を映し込んだ聖湖や周りの山々が見えてきます。近づくと湖面をわたる風(fēng)が気持ちよくて、しばらく景色を見ながら佇んでしまいました。取材中だったことを思い出し、近くを見るとヌマトラノオが白い花をつけて風(fēng)に揺れていました。湖面近くではユウスゲが數(shù)本、長(zhǎng)い莖の先にレモンイエローの花をつけていました。夕方4時(shí)を回っているので、ちょうど咲き始めたところのようです。この花は一日花なので、明日の晝にはしぼんでしまいます。事務(wù)所に戻ってみると、春に訪れた時(shí)にギンリョウソウが咲いていた辺りに、変わったキノコが生えていました。シロヒメホウキタケかカレエダタケのようです。踴りでも踴っているようなユニークな形をしています。




■左:ヌマトラノオ(沼虎の尾) サクラソウ科オカトラノオ屬
本州から九州の濕地や水辺に生育する多年草。6~8月、5裂した白色の小さな花を直立して穂狀につける。地下莖を伸ばして殖え群生する。同じ屬のオカトラノオに対して沼地に生えることからついた名。トラノオは花穂を虎の尾に見立てた名。
■中:ユウスゲ(夕菅) 別名キスゲ ユリ科ワスレグサ屬
本州から九州の山地の草地や林の縁に生育する多年草。7~9月、頂部で枝分かれした1~1.5cmの花莖にレモンイエローの花をつける。花は夕方から咲き始め翌日の晝前には閉じる1日花。夕方に咲き、葉がカヤツリグサ科のスゲに似ていることからついた名。
■右:シロヒメホウキタケ(白姫箒茸)かカレエダタケ(枯枝茸)
?シロヒメホウキタケ:シロソウメンタケ科シロヒメホウキタケ屬
夏から秋に腐葉土や腐木に発生する。名前の通り白色で、傘は無(wú)くほうき狀。
?カレエダタケ:カレエダタケ科カレエダタケ屬
夏から秋に林內(nèi)の地上に群生する。白色から淡い黃白色で細(xì)かい枝が集まったような形をし、枝先はとさか狀になる。
 蕓北の林は落葉樹の種類が多いためか、西日本にありながら関東北部や東北地方の林に近い印象を受けます。初春の樹々の芽吹きから始まり、夏の爽やかな緑影、秋の紅葉など、季節(jié)の変化を存分に楽しむことができます。中でも、聖湖湖畔のヤナギが芽吹く頃と、紅葉の時(shí)期はとてもきれいですので、出かけてみてはいかがでしょうか。
蕓北の林は落葉樹の種類が多いためか、西日本にありながら関東北部や東北地方の林に近い印象を受けます。初春の樹々の芽吹きから始まり、夏の爽やかな緑影、秋の紅葉など、季節(jié)の変化を存分に楽しむことができます。中でも、聖湖湖畔のヤナギが芽吹く頃と、紅葉の時(shí)期はとてもきれいですので、出かけてみてはいかがでしょうか。 ※上記寫真はすべて平成22年8月撮影
※上記寫真はすべて平成22年8月撮影